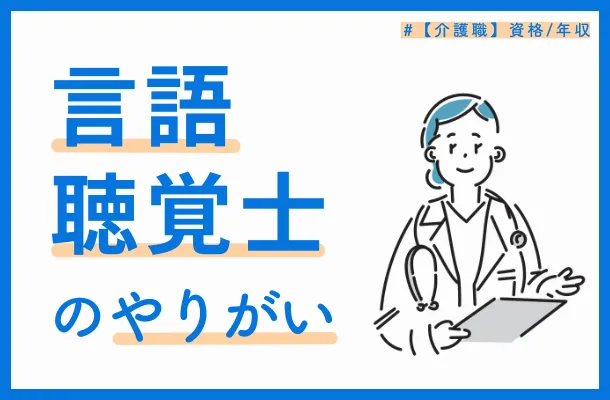資格・就職・転職
投稿日:
2023-04-27
更新日:
2025-07-24
言語聴覚士はどんな仕事?待遇や年収・資格の取得方法を解説!
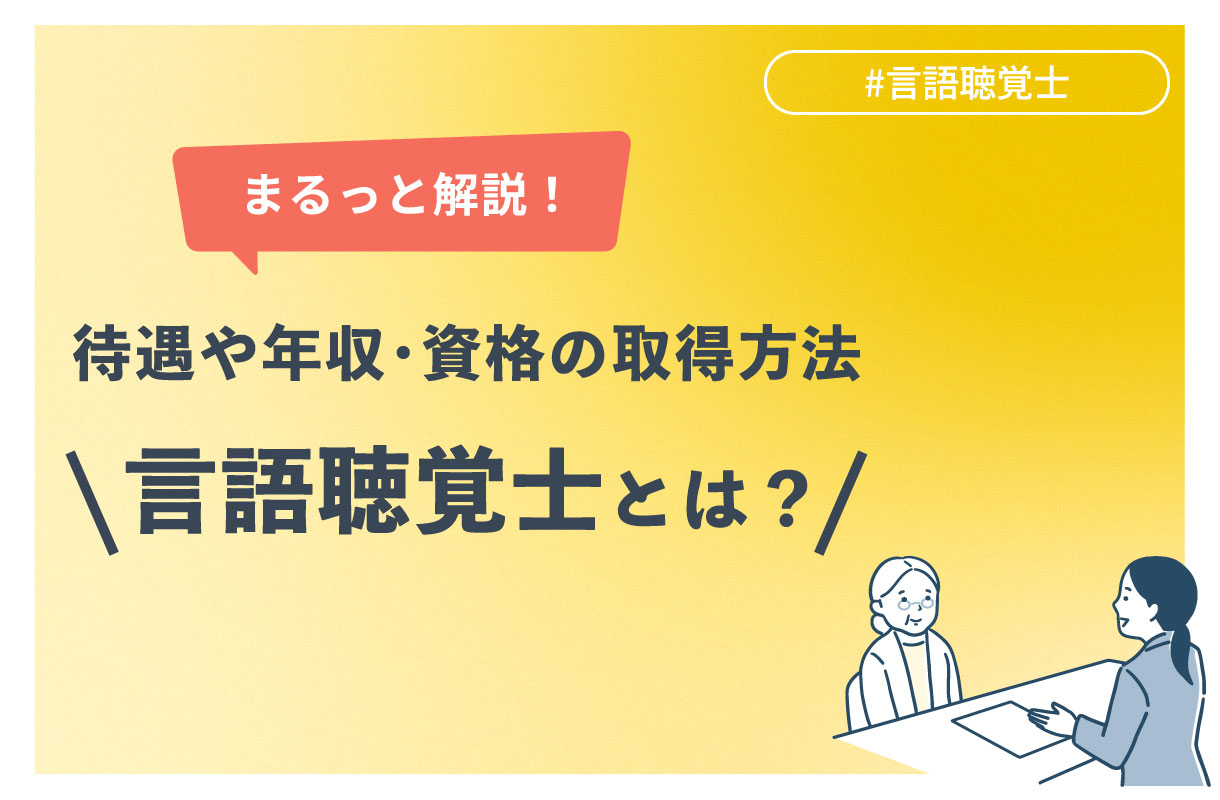
言語聴覚士は、食べたり話したりする機能に障害がある人に対して、リハビリテーションをする専門家です。
言葉によるコミュニケーションや嚥下能力(飲み込み)は日常生活に重要なものです。しかし、病気や事故が原因で、言葉によるコミュニケーションや嚥下が難しくなる場合もあります。また、言葉は子どもの発達にも大きく関わっています。
今回は、言語聴覚士の業務内容や待遇・資格の取得方法について解説しています。
言語聴覚士ってどんな仕事?

言語聴覚士は、脳梗塞や認知症、事故が原因で、聞き取り・発語・言語理解などに障がいがある方、食事の飲み込み(嚥下)が難しい方をサポートする専門職です。
言語聴覚士の具体的な業務内容は、次の通りです。
・食事や嚥下に関する指導
・発声や発語、発話に関する指導
・言語障害の指導
・聴覚支援
・子どもの言葉の訓練
成人や高齢者の場合、病気や事故などが原因で、言語聴覚士による指導が必要となる場合がほとんどです。一方、子どもは、発達障がいや知的障がい・聴覚障がいによって言葉の遅れや周囲に関心が向かないことがあります。そのような子どもに言葉や単語を覚えてもらうことで、コミュニケーション自体に興味を持ってもらうことも、言語聴覚士の仕事のひとつです。
言語聴覚士になるには、国家資格を取得する必要があります。なお、言語聴覚士の試験は、指定試験機関である「公益財団法人医療研修推進財団」が実施します。
言語聴覚士国家試験の概要は、以下の通りです。
| 資格名 | 言語聴覚士 |
|---|---|
| 試験地 | 北海道・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県 |
| 受験手数料 | 38,400円 (※期限までに公益財団法人医療研修推進財団が指定する銀行または郵便局の口座に振り込む) |
| 試験内容 | ・基礎医学、・臨床医学、音声・言語 ・聴覚医学、心理学、失語 ・高次脳機能障害学、発声発語 ・嚥下障害学および聴覚障害学 など |
| 公式ホームページ | 公益財団法人医療研修推進財団 PMET |
※2025年7月3日時点の情報
関連記事:言語聴覚士は人手不足?言語聴覚士の就職・転職や将来性を解説!
言語聴覚士になるには?資格取得までのステップ

言語聴覚士の資格を取得するためには、まずは国家試験に合格する必要があります。ここでは、次の2点について解説します。
国家試験の概要と合格率
言語聴覚士の国家資格の受験対象は、都道府県知事が指定した言語聴覚士養成学校で、必要な知識や技能を習得した方です。
言語聴覚士養成学校には、高等学校卒業者、短期大学や専門学校、一般的な4年制大学の卒業者が入学できます。ただし、養成学校で学ぶ期間は、最終学歴や入学課程によって異なります。
言語聴覚士養成学校の合格率は以下の通りです。
| 受験年度 | 合格率 |
|---|---|
| 第27回(2025年) | 72.9% |
| 第26回(2024年) | 72.4% |
| 第25回(2023年) | 67.4% |
参考:厚生労働省|第27回言語聴覚士国家試験の合格発表について、厚生労働省|第26回言語聴覚士国家試験の合格発表について、厚生労働省|第25回言語聴覚士国家試験の合格発表について をもとに作成
合格率は例年60%台後半〜70%台前半で推移してます。
言語聴覚士の国家試験は年に1回、毎年2月頃に実施されます。2025年2月実施の27回試験では、1問1点で配点され、198点満点のうち、119点以上が合格でした。
(※2025年5月時点の情報です、最新情報については厚生労働省の言語聴覚士国家試験の公式ホームページでご確認してください)
資格取得までには一定の年数がかかる
言語聴覚士の資格を取得するためには、受験資格を得るための一定の年数が必要です。
次の表は、言語聴覚士の資格を取得するまでの一般的なルートをまとめたものです。ここでは高等学校と一般的な4年制大学の2つについて取り上げます。
| 高等学校 | ➡︎文部科学大臣指定の大学・短大・専修学校を卒業し、その後、言語聴覚士養成校(1~2年)に入学・卒業する ➡︎言語聴覚士の養成校(3~4年)を卒業する |
| 一般の4年制大学 | 指定大学・専修科(または、2年制の専修学校)を卒業する |
指定された養成校に在籍し、専門知識や技術を習得した方を対象に、受験資格が得られます。そのため、養成校に通わず独学や通信教育では資格を取得することはできません。社会人の場合、夜間課程の養成校に通うという方法を選べば、仕事を両立しながら言語聴覚士の受験資格を取得することが可能です。
言語聴覚士の平均年収や待遇、年収アップの方法
言語聴覚士の待遇は、働く場所や地域によって異なります。ここでは、言語聴覚士の平均年収や働く場所・キャリアの磨き方について解説します。
平均年収と働く場所による違い
国税庁が発表した「民間給与実態統計調査」によると、2023(令和5)年の全国平均年収は460万円でした。一方、言語聴覚士の2024(令和6)年の平均年収は、444.2万円となっており、全国平均よりもやや低い水準です。
参考:国税庁|令和5年分民間給与実態統計調査結果について、厚生労働省| job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))言語聴覚士(ST)
下記の表は、他の専門職と比較したものであり、医療職と比べると低いことがわかります。
| 職種 | 平均年収 |
|---|---|
| 言語聴覚士 | 444.2万円 |
| 看護師 | 519.7万円 |
| 薬剤師 | 599.3万円 |
参考:厚生労働省| job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))言語聴覚士(ST)、
厚生労働省| job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))看護師、厚生労働省| job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))薬剤師をもとに作成
また、2023(令和5)年の賃金構造基本統計調査から、全国の言語聴覚士の給料を地域ごとに比較すると、最も高い給料は茨城県の約33万円でした。一方、給料が低い地域では約25万円となっており、約7万円の差が生じています。
年収を上げるためのスキルとキャリアの磨き方
前述の通り、言語聴覚士は全国平均を下回る年収ですが、個人の努力次第で年収を上げることが可能です。例えば、次のような方法が考えられます。
・言語聴覚士の経験年数を積み重ね、施設内で役職に就く
・今より給料の高い職場に転職する
・副業をする
言語聴覚士としての経験を重ねることで、施設内での評価を高められれば、主任やリーダーといった役職に就くことが可能です。
言語聴覚士の多くは医療機関や介護施設で働いており、中でも訪問リハビリは1件あたりの単価が比較的高いため、給料が高くなる傾向です。訪問リハビリ施設の中には、インセンティブ制を運用している施設もあり、基本給に加えてボーナスが上乗せされる可能性も考えられます。
言語聴覚士は、基本的に残業や休日出勤はほとんどありません。訪問リハビリやデイケアでは、1日数時間で募集している場合もあるため、1週間のうち1日を副業に充てることも可能です。ライティングといったパソコンを使えば自宅で作業できる仕事も見つけられるでしょう。
ただし、副業する場合は、本業や私生活に支障をきたさぬよう体調管理が重要です。日頃から疲れがでないよう対策が必要です。
広がる活躍の場!言語聴覚士の専門性が生かせるフィールド
近年では働き方が多様化しており、ライフワークバランスも重要視されています。言語聴覚士は日中の活動が多く、ライフステージがあっても継続して働きやすいといえるでしょう。
また、言語聴覚士は言語訓練や構音障害(※1)のリハビリの分野で独立することも可能なため、訪問リハビリテーションやことばの教室で、柔軟な形で専門性を発揮できる機会が増えています。
言語聴覚士は、医療・福祉分野だけでなく、教育現場や企業、AI分野などでも活躍の場が広がっています。ここでは、言語聴覚士の新たな専門性を生かせるフィールドを紹介します。
(※1)脳や神経の病気により唇や舌などの筋肉に適切な指令が働かず、発音に障害が生じること
教育現場で後進を育成
言語聴覚士の専門性を行かせる重要なフィールドのひとつとして、未来の言語聴覚士を育成する教育現場があります。専門学校や養成校では、自分の経験や、習得した知識・実践的なスキルを学生に伝えることで、専門職としての社会貢献にもつながるだけでなく、自身のキャリアを磨き上げる機会にもつながります。
保育所や小学校・特別支援学校の現場でも、言語聴覚士は講師として活躍しています。発達障害や聴覚障害、発音障害の子どもたちは支援を必要としており、保育士や教員と連携しながらサポートすることも少なくありません。
また、言語聴覚士は保護者や教員向けのセミナーを開催し、障がいに関する知識と適切な関わり方を学ぶ機会を提供することもあります。子どもたちへの適切な関わり方を知ることで、一緒に課題に取り組めるでしょう。
医療以外での言葉の専門家
近年では、企業が従業員の健康維持や病気予防のためにウェルネスプログラムを実施しており、言語聴覚士はその支援に関わる場合があります。
また、言語聴覚士の専門知識や経験を生かして、書籍やコラムの執筆、ブログ作成などで、医療記事の執筆や監修をすることも可能です。
近年では医療業界にもAIやICT技術など、テクノロジーの力が取り入れられているため、リハビリテーションにおけるAIへの指示やアプリ開発の実装監修なども行われています。
AI時代の人間にしかできない支援者
AIの発展に伴い、「言語聴覚士の仕事はなくなるのでは?」という声も上がるでしょう。確かに、AIは大量の言語情報を処理できるため、記録や書類作成、情報整理などに役立つのは事実です。
一方で、AIやロボットには人間の言葉の裏にある感情や意図といった非言語的なコミュニケーションを読み解くことは難しいと言われています。言語聴覚士は、利用者それぞれの生活背景や価値観、身体状況を汲み取ったうえで訓練や指導を行える専門職といえるでしょう。
また、AIやロボットは、人間の膝や足の関節などの大きい動作にはある程度対応できますが、手首や指、肩などの細やかな動きには、現時点ではすべて対応していません。
こうした観点からも、言語聴覚士の仕事はAIによって完全に代替することは難しく、相手の感情や状況に寄り添いながら適切な支援を行えることこそが、言語聴覚士ならではの大きな強みといえるでしょう。
言語聴覚士は専門性を生かし未来を切り拓ける仕事

言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや嚥下に課題を抱える方を、サポートする仕事です。言葉は子どもの発達にも関わることから、子どもから高齢者まで幅広く年齢をサポートできる専門性の高い職業だといえます。
資格を取得するためには指定養成校を卒業し、国家試験に合格する必要があります。夜間に学べる養成校もあるため、働きながら言語聴覚士の勉強をすることも可能です。
言語聴覚士は、利用者さんから感謝の声に触れる機会にも巡り合うことができるため、社会に貢献できるやりがいのある仕事です。医療・福祉現場はもちろん、教育、企業、AI技術と連携した新たな分野など、活躍のフィールドは広がり続けています。
言語聴覚士は自身の専門性を十分に生かせる社会の未来を切り拓ける魅力的な職業といえるでしょう。
コラム記事執筆者

山本史子
介護福祉士
デイサービスで10年以上、介護福祉士として現場勤務を経験。利用者さまに「またデイサービスに行きたい」と思ってもらえる施設づくりを目指し、日々ケアに携わっている。趣味は工作やハンドメイドで、利用者さまとのコミュニケーションにも活かしている。現在は、介護現場での勤務と並行してライターとしても活動中。現場経験に基づき、実用的で温かみのある記事執筆を心がけている。