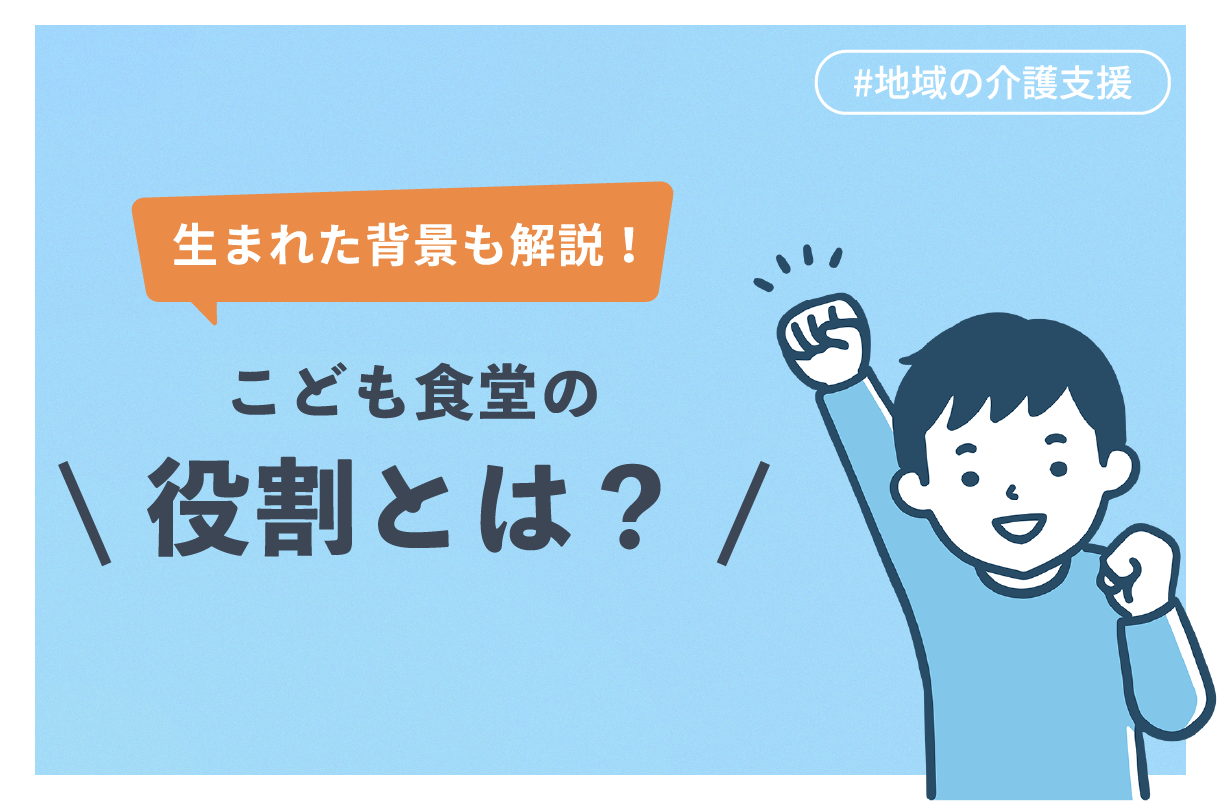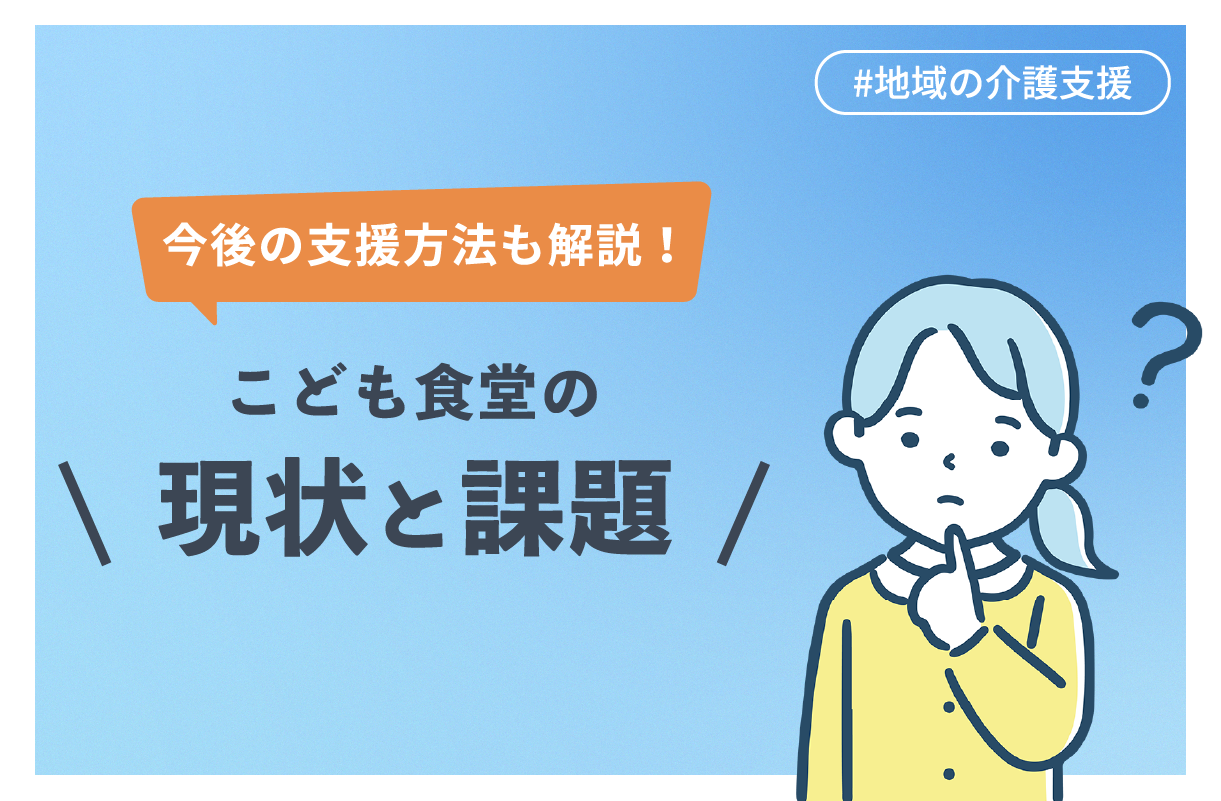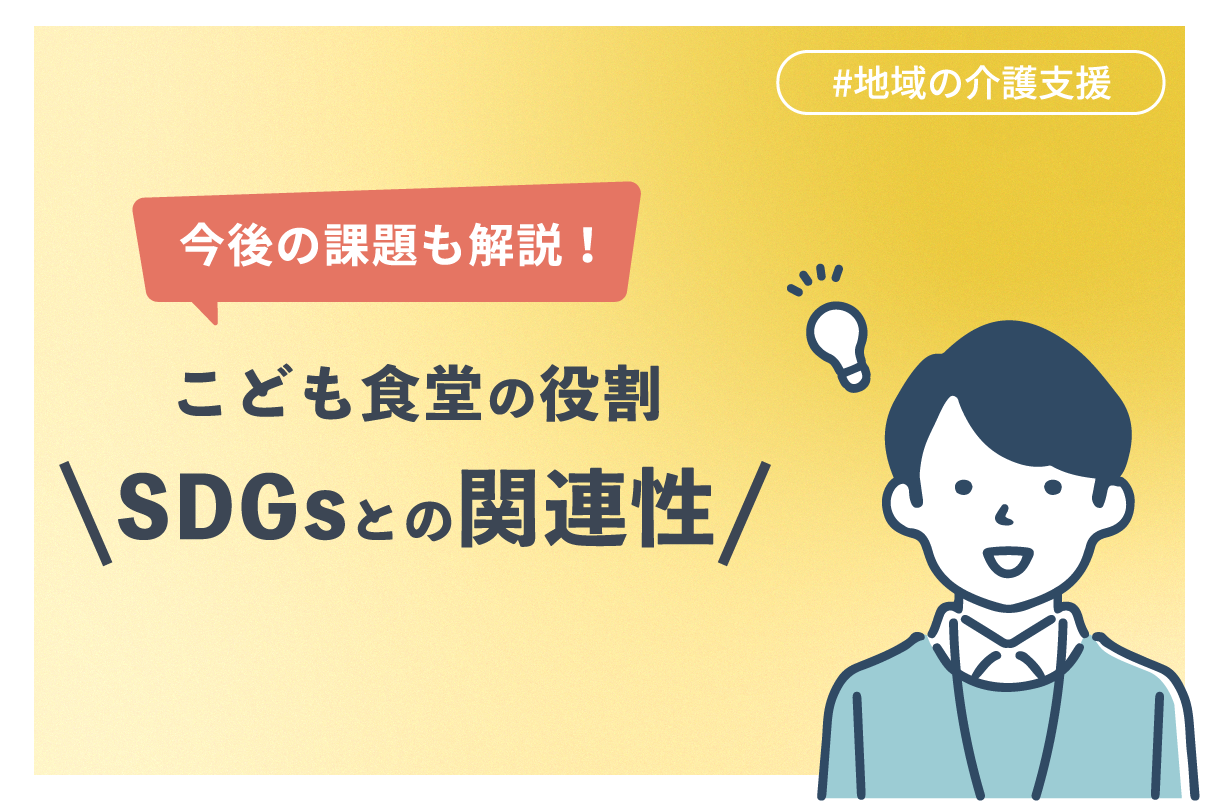ヤングケアラー・若者ケアラー
投稿日:
2025-04-04
更新日:
2025-04-18
【インタビュー】こども食堂が紡ぐ希望。機会格差に挑む21歳の未来図~後編~

2021年に開設された熊本市の「ふるさと元気子ども食堂」は、月2回の開催で、毎回100名以上が訪れる地域の居場所として定着しています。多い月には200名を超える参加者が集まることもあり、その需要の大きさを物語っています。
前編インタビューでは、ふるさと元気子ども食堂の代表の宮津航一さんが、こども食堂を始めたきっかけとその基本的な活動について紹介しました。今回の後編インタビューでは活動を通じて見えてきた課題と、こども食堂ならではの役割、そしてこれからの展望を聞きました。
「なぜ必要なの?」から「なくてはならない存在」へ

子どもの貧困が社会問題として認識される一方で、宮津さんがふるさと元気子ども食堂を立ち上げた当初、地域におけるこども食堂の役割は手探りの状態だったそうです。宮津さんは、創設当時のことを振り返りながら語ります。
宮津さん(以下、宮津):子ども食堂を立ち上げた当初は、「なぜ、こども 食堂が必要なのか」と問われることも多かったですね。ただ、その状況は次第に変化し、今では「(ふるさと元気子ども食堂のおかげで)子どもたちの様子が明るくなった」「家庭での良い変化が見られた」という声が寄せられるようになりました。
「子どもたちの成長には、学校だけでなく、地域全体で支える視点が必要」という考えのもと、地域や子どもに関わる団体との協力関係も深まり、互いの強みを活かした支援の輪が広がっています。
特に重要なのは、行政機関やスクールソーシャルワーカーとの連携による多角的な支援体制です。行政機関からの紹介で食堂を利用し始めることもあれば、逆に食堂のスタッフが利用者の気になる様子に気づき、専門機関につなぐこともあります。このように支援の輪が多方向に広がり、連携することで支援を本当に必要とする家庭への適切なサポートが実現し、「誰一人取り残さない地域づくり」が進んでいることを実感しています。
見えにくい「機会の格差」への取り組み
「地域の子どもは地域で育てる」という意識が根付きつつある中で、宮津さんが次に注目したのは、子どもたちの間に存在する「機会の格差」でした。ふるさと元気子ども食堂では、イベントの実施を通じて、その格差の解決に尽力しています。
宮津:習い事や体験活動、人との出会いなど、子どもの成長に重要な機会が、家庭環境によって大きく異なることがあります。この差は子どもたちの将来に大きな影響を与えかねません。
例えば、家族や仲間で、季節の思い出づくりとしてBBQやブルーベリー狩りといった屋外活動をやってみたいと思っても、準備や費用の面で難しいご家庭も存在します。ふるさと元気子ども食堂では、そうした子どもたちを対象に地域のボランティアの協力をのもと、季節に応じたイベントを企画しています。イベントに参加した経験が、将来の可能性を広げるきっかけにつながるかもしれません。
ふるさと元気子ども食堂では、学校、行政、地域ボランティアとの連携をしながら、子どもたちの「やってみたい」という気持ちを尊重しています。また、子どもたちの成長を支える新たな取り組みも続けています。
心の居場所としての意義
ご自身の幼少期に経験した地域との温かいつながりが、心の支えとなり、「人としての土台を築くうえで欠かせないもの」と宮津さんは振り返ります。
宮津:現在、子どもが情緒的な基盤をつくる場所が家庭だけになりがちですよね。でも、人とのつながりをつくり、大切にされているという実感を得ることは、将来の大きな心の支えになります。つらいことがあっても踏みとどまれる力になるでしょう。
私も幼い頃、地域のおじちゃんやおばちゃんに「こうちゃん」と呼ばれ、かわいがってもらった記憶があります。家族以外にも、自分のことを知っていて、考えてくれている人がいるというのは、心の大きな支えになります。特につらいときや、自分の存在が認められていないと感じたときに、家の外にも自分のことを応援してくれる人の存在は大きいですよね。
こども食堂に通い始めて変わった子どもも多いと思います。以前は口数が少なかった小学生が、今では積極的に会話を楽しむようになっています。不登校気味だった中学生が、食堂での経験をきっかけに少しずつ学校に通えるようになった事例もあります。
また、宮津さん自身の生い立ちへの理解が、多様な背景を持つ家庭との信頼関係構築にもつながっているそうです。
宮津:私の背景を知っているからこそ、普段は話しにくい自分の境遇について打ち明けてくださる方も多いんです。そういう意味で、ふるさと元気子ども食堂が安心してつながれる場所になってくれているのかもしれません。
日常のつながりは地域防災にも

2016年に発生した熊本地震は、宮津さんにとって、地域のつながりの重要性を実感させる出来事でした。被災地では、日頃から地域のつながりが強かった地域ほど、避難所運営や支援物資の配布がスムーズに進んだという教訓が残されました。宮津さんは熊本地震の経験を通して、こども食堂と防災についても言及しています。
宮津:災害時に最も頼りになるのは近隣住民です。しかし、日常的な交流がなければ、緊急時の助け合いは難しいでしょう。こども食堂での日々の触れ合いは、いざという時の地域の支え合いを支える土台となっているので、学生ボランティアとの遊びの時間も大切にしています。
実際に、こども食堂では、地域のボランティアによる工作教室や、自転車発電でポップコーンを作る体験など、さまざまな企画を通して子どもたちの笑顔があふれかえっています。
宮津:イベント後の保護者から「兄弟がいない一人っ子なので、他の子どもたちと遊ぶ機会が持てて助かります」「母親の私も落ち着いて食事ができてありがたいです」といった感想が寄せられています。子どもたちからは「お兄ちゃんお姉さんと遊べるのが楽しみ」という声も。また、学生ボランティアの姿に触発され、「大きくなったら自分もボランティアとして参加したい」という子どももいます。このように世代を超えた交流は、子どもたちの将来の選択肢も広げているのが実感できますよね。
新しい時代の絆のかたちとしてのこども食堂
宮津さんは、「昔は良かった」とただ単に振り返るだけでなく、今の時代の流れにあったこども食堂の運営を模索しています。
宮津:確かに地域のつながりは大切ですが、それが窮屈なものになるのは良くありません。現在のライフスタイルや多様な価値観を受け入れながら、行きたいときに足を運び 、参加したいときに参加できるといった「緩やかなつながり」を作ることが大切だと考えています。そのためにも善意だけに頼らない、継続的な活動の仕組みづくりを目指しています。
例えば、地元企業との連携を強化して、食材の提供や社員のボランティア参加など、企業の社会貢献活動と連携することで、安定的な運営基盤の確保を図るようにしています。
こども食堂は新しい時代の公共空間として機能し始めています。ここでの出会いや体験が、子どもたちの未来を明るく照らす一助となればいいですよね。それが私たちの願いです。
最後に~未来を築く子どもたちへ~

(写真左前)祐麻さんの長男 悠叶(はゆと)くん
子どもたちは、自分の未来をどのように思い描いているだろうか。また、私たち大人は、その夢や希望をどう支えることができるのか――。
宮津さんはこの問いに向き合いながら、こども食堂の活動を通じて子どもたち一人ひとりが自分の可能性を信じられる社会づくりの実現に取り組んでいます。
宮津:子どもたちには、自分の生い立ちや環境を受け止め、それをプラスに捉えてほしいと思っています。そのためには、周りの大人たちが温かく見守り、支える存在であることが大切です。
また、子どもたちの成長を多角的に支援する体制づくりとして、学習支援の場の設置や、地域の専門家と連携した相談窓口の開設などが進められています。これらの取り組みは、誰もが安心して暮らせる社会づくりへとつながる、確かな一歩となっています。こども食堂の活動の本質について、宮津さんは持論を語られています。
宮津:活動を続けること自体が目的ではありません。本当に必要とされている活動なら、必ず誰かが引き継いでくれるはずです。私たちが目指すべきは、子どもたちが安心して成長できる環境をつくることです。
最後に宮津さんは、子どもたちへのメッセージを力強く語っていただきました。
宮津:人生は一度きりです。たとえ恵まれない環境に置かれていたとしても、そのことで自分の未来を暗くする必要はありません。子どもたちには、明るい未来を描いてほしい――。なぜなら、子どもたちこそが未来をつくる存在なのですから。
今回はお忙しいところ、インタビューに応じていただきまして、ありがとうございます。
宮津さまのさらなるご活躍をお祈りするとともに、こども食堂の今後の展開にも目が離せません。
前編インタビュー記事はこちら

2003年生まれ。2007年、慈恵病院(熊本市)のこうのとりのゆりかごに預けられる。同年、里親の宮津美光・みどり夫妻のもとへ委託。2021年に普通養子縁組を成立し、同年ふるさと元気子ども食堂を開設。2022年、こうのとりのゆりかごに預けられた生い立ちを公表。熊本朝日放送ドキュメンタリー2022はじめ多数のメディアに取り上げられる。2023年、国際ソロプチミスト日本財団学生ボランティア賞受賞。講演活動も多数行っている。現在、熊本県立大学総合管理学部総合管理学科在学中(※2025年4月時点)。ふるさと元気子ども食堂代表。一般社団法人子ども大学くまもと理事長。
宮津 航一 公式ホームページ http://miyatsu-official.net/
宮津 航一 公式Twitter https://x.com/miyatsu_oficial/
ふるさと元気子ども食堂 公式Facebook https://www.facebook.com/hurusatogenki.cs/
ふるさと元気子ども食堂 公式Instagram https://www.instagram.com/hurusatogenki.cs/
取材執筆&撮影担当者

筒井 永英
1985年生まれ。横浜市出身、熊本市在住。津田塾大学卒業後、半導体の特許翻訳者・秘書を経て言葉のニュアンスへの感性を磨き、その後、国土交通省の職員として調整力を培う。また、保険の営業職にも従事し対話力を獲得。2017年に未経験からライターに転身し、企業・自治体の取材や広報サポートなどを行う。執筆した半導体記事はYahoo経済ニュース1位を獲得。ITと地方、女性のワークスタイルに強い関心を持っている。