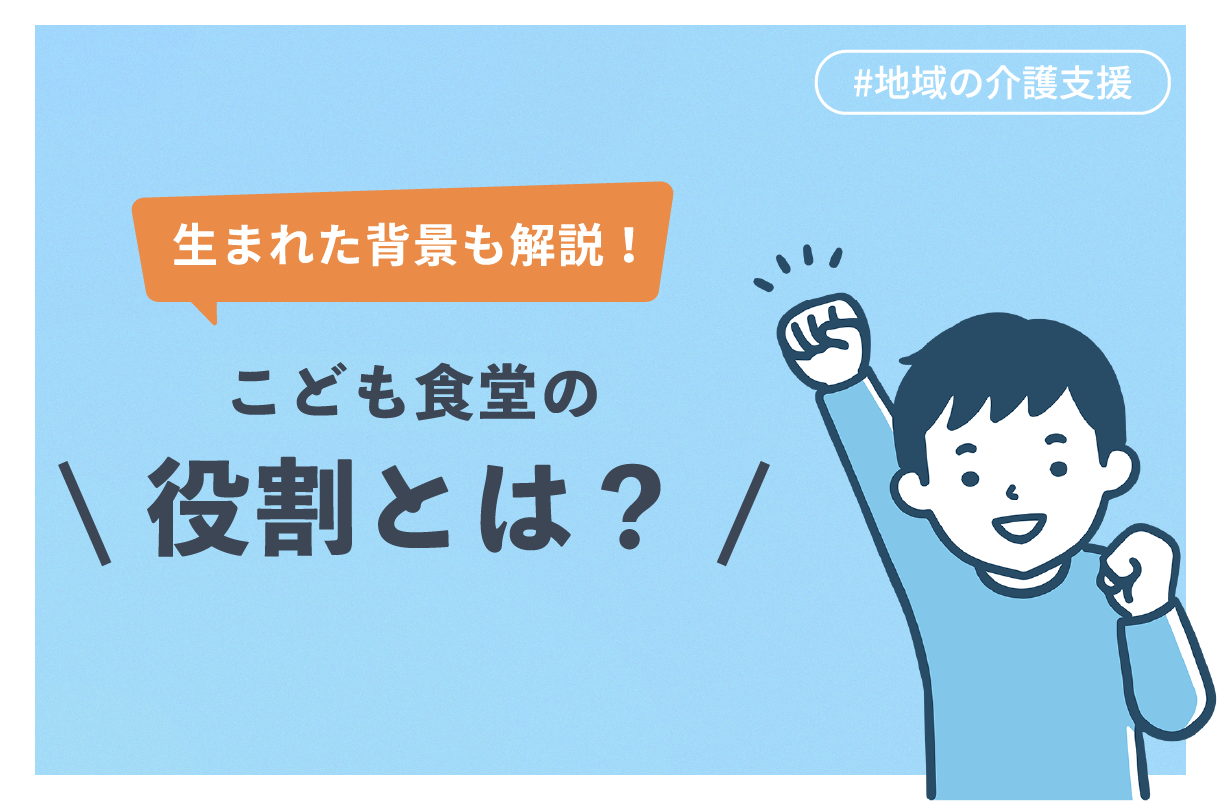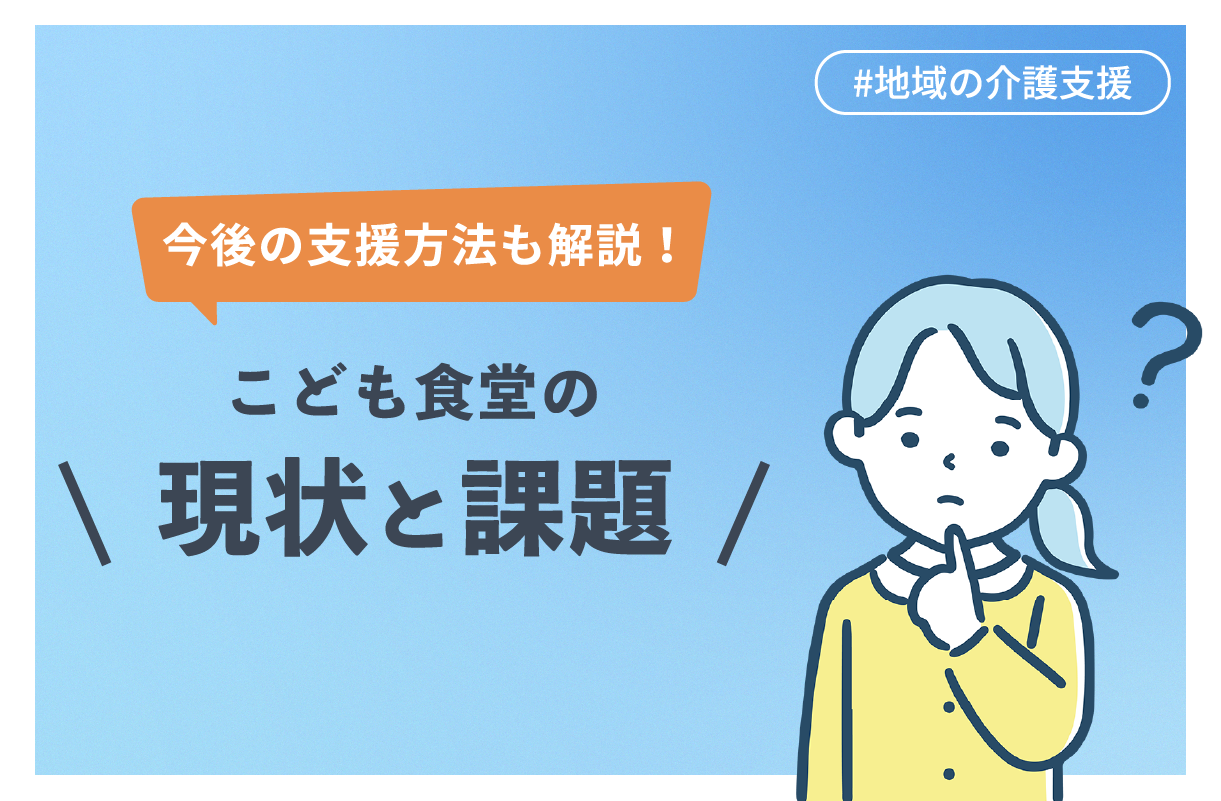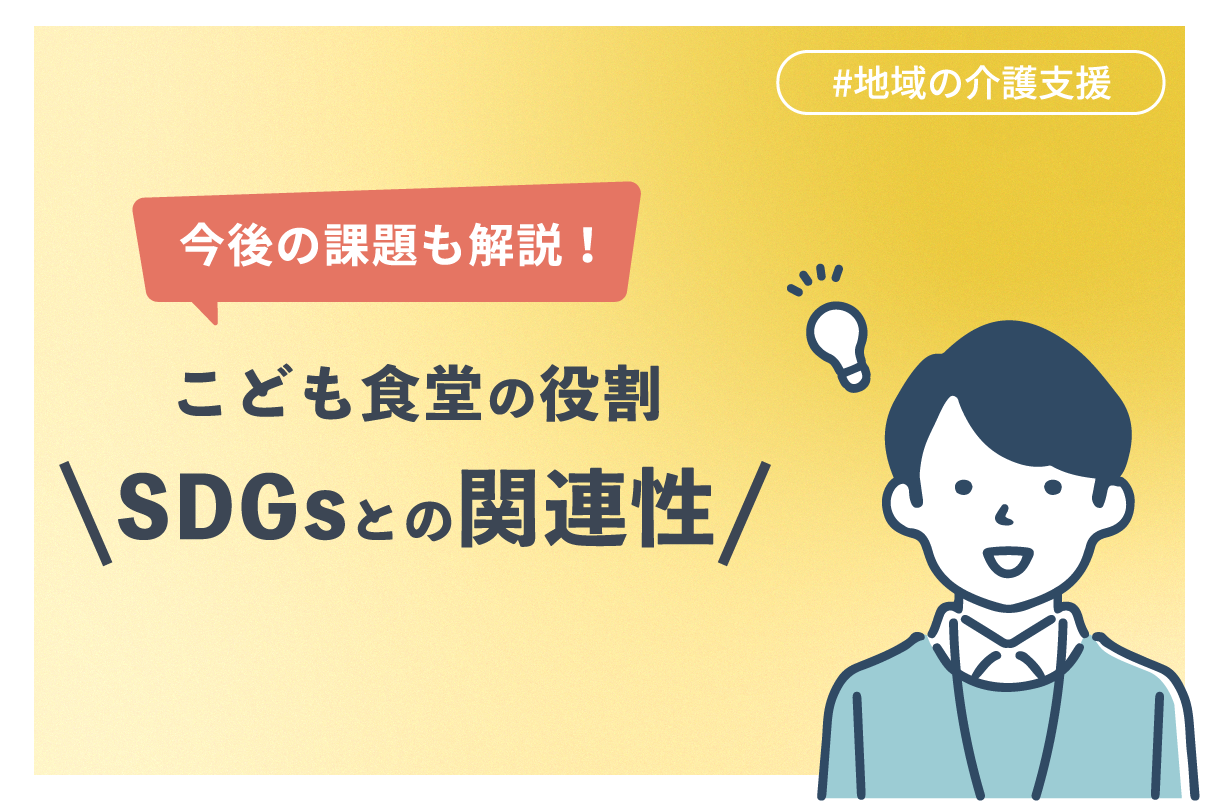ヤングケアラー・若者ケアラー
投稿日:
2025-04-03
更新日:
2025-04-18
【インタビュー】食事支援から交流拠点へ。現役大学生が挑む、次世代こども食堂の取り組みとは?~前編~

「こども食堂」と聞くと、経済的に困窮する子どもたちへの食事支援というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし、この「貧困対策」というレッテルは、かえって支援を必要とする家庭の足を遠ざける要因となっています。「貧困家庭と思われたくない」という気持ちから、地域での見られ方を気にして足が遠のいてしまうご家庭も存在しているのが実情です。
熊本市で「ふるさと元気子ども食堂」を運営する宮津航一さんは、ネガティブな固定観念を打ち破ろうとしています。食事提供にとどまらない、新しい形のこども食堂の取り組みをうかがいました。
現役高校生が始めた地域の居場所

2025年現在、宮津さんは熊本県立大学で行政・福祉を中心に地域のリーダーを育成する総合管理学部で学びながら、月2回のこども食堂の運営や小学生を対象にした教育プログラムを提供する子ども大学など、子どもに関わる複数の事業運営に携わっています。
宮津さんは、2021年6月に地元熊本市で『ふるさと元気子ども食堂』をスタートしました。当時の宮津さんは高校3年生で、コロナ禍。福岡県で起きた男児の餓死事件を知り、いてもたってもいられなくなったそうです。
宮津さん(以下、宮津):ラジオで福岡の悲しい事件のニュースを聞きました。その時に、なぜ地域社会はそれを防げなかったのか…、子どもや親の責任ではなく、社会問題だと強く感じました。
両親の背中を見て、こども食堂開設の道へ
宮津さんがふるさと元気子ども食堂を立ち上げた理由は大きく3つ。そのうち1つはご両親の存在です。立ち上げた背景についてうかがいました。
宮津:私は両親がさまざまなボランティア活動をしている姿を見て育ちました。思ったことを形にしないといけないという気持ちは、両親から学びました。
2つ目は、コロナ禍で子どもたちの地域社会とのつながりが失われていると感じたことです。学校の休校や地域行事の中止により、子どもたちの居場所が急速に失われていきました。
そして3つ目が、福岡県での男児餓死事件です。これらの出来事が、ふるさと元気子ども食堂を開設するきっかけになりました。
コンセプトは「お腹を満たし、心を満たす居場所」
ふるさと元気子ども食堂のコンセプトは「お腹を満たし、心を満たす居場所」です。食事の提供だけでなく、季節のイベントやビンゴ大会、学生ボランティアとの交流など、地域とのつながりを感じられる工夫を凝らしています。
宮津:食事を入り口に、子どもたちの居場所を作りたいと思いました。子どもの居場所は、親の居場所にもなり、そこに地域の人々が集まることで、地域全体の居場所になっていく――。子どもは、人と人をつないでくれる存在なんです。
運営するこども食堂の特徴は、未就学児とその保護者の利用が多い点です。コロナ禍であっても運営を一度も中止せず、親子での参加を呼びかけてきました。感染対策も入念に行い、座席の間隔を広げ、換気を徹底し、食事の提供方法もビュッフェ形式から個別配膳に変更するなど、細かな配慮を重ねてきました。
こども食堂を通じて見えない課題に寄り添う
宮津さんは、親子でふるさと元気子ども食堂に足を運んでもらうよう促しています。それは、食事の提供以上に重要な役割があるためです。
宮津:食堂で親子の様子を見ていると、それぞれの関係性や声かけの仕方の特徴が見えてきます。親御さん自身も、他の家庭との関わりを通じて、自分の子育ての方法について新たな気づきを得られることがあります。
核家族化が進んだ現代は、家庭内の状況が見えづらい時代です。そんな中、こども食堂は親子関係を見守り、支援の必要性を見極める場としても機能しています。実際、当初は食事提供だけを目的に訪れていた親たちが、次第に育児の悩みを打ち明けてくれるようになるケースも増えています。
宮津:食事を受け取るだけなら、親だけの来訪でも可能です。でも、親子一緒の参加を呼びかけることで、家庭内では見えにくい親子関係の課題に気づき、必要な支援につなげられることもあります。それがこども食堂の重要な役割の一つといえるでしょう。
支援の壁を超えて

本当に支援を必要とする家庭ほど、こども食堂に足を運びにくい現実もあるそうです。「貧困対策」というレッテルが、かえって支援を必要とする人々の足を遠ざけていると、宮津さんは言及していました。
宮津:貧困の子どもだと思われたくないから、その親が一方的にこども食堂に行くのを引き留めるケースもあります。こども食堂が地域にあることで、その地域が貧困地域だと思われることを懸念する声も上がっています。
この課題に対して、私は「誰もが気軽に立ち寄れる場所づくり」を心がけています。ふるさと元気子ども食堂は、校区外から来られる利用者も多いですね。実際に熊本市街、益城町や大津町、玉名市からも訪れることもあります。単に食事をするだけなら、近所の食堂でも構いません。でも、ふるさと元気子ども食堂には、人とのつながりや温かい雰囲気を求めて来てくださる方が少なくありません。
こども食堂の運営の実態と課題とは?
熊本県内には約166のこども食堂があり(※2024年1月末時点)、九州では2番目に多い数値です。特に、熊本県では、2016年の熊本地震のあとに地域のコミュニティの必要性から急増しています。しかし、運営面では課題も多いとのことです。
宮津:熊本のこども食堂は、地域のおばあちゃんたちが立ち上げているケースが多いですね。熱い想いで取り組んでいますが、組織としてはまだ弱い面があります。具体的な課題として、ボランティアスタッフの高齢化や後継者不足、食材の調達、衛生管理の徹底などが挙げられます。特に深刻なのは運営資金の問題です。
現在、私の子ども食堂は寄付金だけで運営していますが、将来的には助成金の活用も検討しています。ボランティアの善意だけに頼るのではなく、持続可能な運営体制を作っていく必要があります。ただし、それが活動の本質を損なわないよう、慎重に進めていきたいですね。
地域全体で支える仕組みづくりが子どもの健やかな成長につながる
運営面での課題に直面する中、宮津さんは従来のこども食堂の枠を超えた、新しい形を模索しています。
宮津:今の社会は、愛情や支えが家庭の中だけに閉じこもりがちです。以前は三世代同居も多く、家庭内でも地域でもさまざまな形で愛情が満たされていました。
でも今は、それが家庭だけの責任になっています。その解決策として、こども食堂を地域の交流拠点として位置づけ直すことを提案しています。ふるさと元気子ども食堂でも大学生のボランティアや地域の高齢者など、さまざまな立場の人々が運営に関わることで、新たなつながりが生まれています。
こども食堂のスタッフやボランティアは、活動終了後にそれぞれの地域に戻ってきますが、食堂の開催日以外でも互いに声を掛け合える関係性が自然と育まれています。地域との密接な関係は、ボランティアの確保や食材の調達といった運営面での課題解決にもつながっています。
何より、多くの地域住民が「自分ごと」として意識することで、子どもたちの成長を見守る体制が着実に根付くと同時に、持続可能な運営体制の構築に発展していくでしょう。
地域のつながりが育む希望の種

(写真左前)祐麻さんの長男 悠叶(はゆと)くん
宮津さんはふるさと元気子ども食堂の活動を通じて、「自分の生い立ちや置かれている環境を、できるだけプラスに捉えて欲しい。その中で可能性を見出し、視野を広げて、前向きに歩んでいってほしい」と子どもたちに希望を持ってほしいと話していました。
こども食堂は、食事提供の領域にとどまらず、地域社会のつながりを再構築し、子どもたちの未来を支える重要な場所になりつつあります。その役割は今後さらに重要になることでしょう。
宮津さんの挑戦は、地域社会に確かな変化をもたらしています。しかし、その活動の中で新たな課題も浮き彫りになっています。こども食堂は地域の「絆」をどのように紡ぎ直していくのか――。
後編インタビューでは、活動を通じて浮かび上がった「機会の格差」の問題と、未来への展望についてうかがいます。
後編インタビュー記事はこちら

2003年生まれ。2007年、慈恵病院(熊本市)のこうのとりのゆりかごに預けられる。同年、里親の宮津美光・みどり夫妻のもとへ委託。2021年に普通養子縁組を成立し、同年ふるさと元気子ども食堂を開設。2022年、こうのとりのゆりかごに預けられた生い立ちを公表。熊本朝日放送ドキュメンタリー2022はじめ多数のメディアに取り上げられる。2023年、国際ソロプチミスト日本財団学生ボランティア賞受賞。講演活動も多数行っている。現在、熊本県立大学総合管理学部総合管理学科在学中(※2025年4月時点)。ふるさと元気子ども食堂代表。一般社団法人子ども大学くまもと理事長。
宮津 航一 公式ホームページ http://miyatsu-official.net/
宮津 航一 公式Twitter https://x.com/miyatsu_oficial/
ふるさと元気子ども食堂 公式Facebook https://www.facebook.com/hurusatogenki.cs/
ふるさと元気子ども食堂 公式Instagram https://www.instagram.com/hurusatogenki.cs/
取材執筆&撮影担当者

筒井 永英
1985年生まれ。横浜市出身、熊本市在住。津田塾大学卒業後、半導体の特許翻訳者・秘書を経て言葉のニュアンスへの感性を磨き、その後、国土交通省の職員として調整力を培う。また、保険の営業職にも従事し対話力を獲得。2017年に未経験からライターに転身し、企業・自治体の取材や広報サポートなどを行う。執筆した半導体記事はYahoo経済ニュース1位を獲得。ITと地方、女性のワークスタイルに強い関心を持っている。