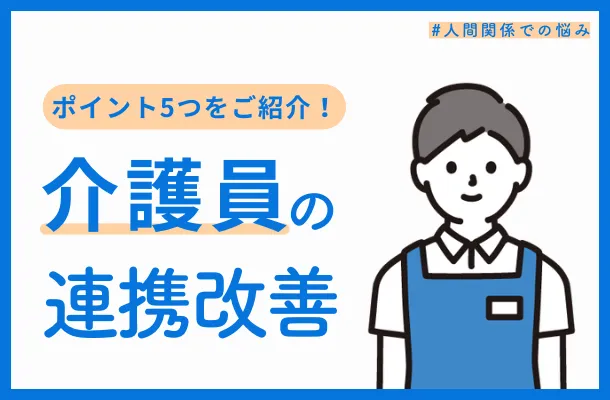介護職のお悩み
投稿日:
2025-07-01
更新日:
2025-07-01
新人介護職員の悩みと対処法を解説!仕事を続けるコツも解説
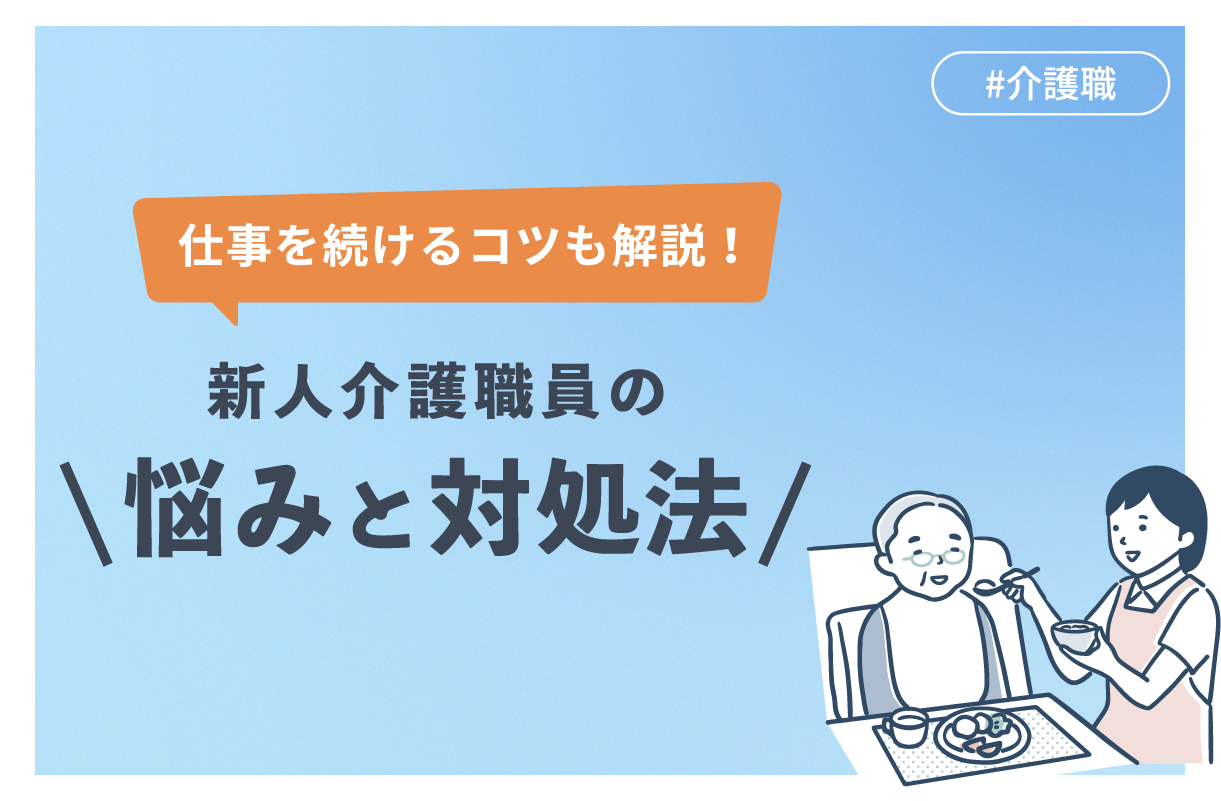
「覚えることが多くて大変」「失敗ばかりで、自分には向いていないかも」など、新しい環境で、このような不安や焦りを感じることはありませんか。
高齢者のケアに携わる介護の仕事は、やりがいが大きい一方で、心身への負担を感じやすいものです。特に新人職員は、慣れない業務や人間関係に戸惑い、時には自信を失うこともあるでしょう。
本記事では、多くの新人職員が直面するリアルな悩みにフォーカスし、具体的な対処法や仕事を続けていくコツを、介護福祉士である筆者の体験談を交えてご紹介します。
仕事で壁にぶつかるのは、誰もが通る道です。この記事を参考に、自分に適切な乗り越え方を探してみてください。
新人介護職員の離職率はどのくらい?

一般的に「新卒の3割が3年以内に離職する」と言われており、介護業界に限らず、初めて社会に出る若者が就職後に直面する壁となっています。
厚生労働省が2024年10月に発表した「学歴別就職後3年以内離職率の推移」によると、2021(令和3)年3月に卒業した新規大学卒の就職者3年以内の離職率は34.9%、新規高卒就職者は38.4%という結果でした。
さらに「令和5年雇用動向調査の結果の概況」の産業別の調査では、2023(令和5)年度の全産業の平均離職率は12.1%でした。介護職を含む医療・福祉分野の離職率は13.3%だったため、介護職の離職率は全体平均を比較しても高いことがわかります。
今、介護職として働いてる方の中には、過去に「つらい」「辞めたい」と思ったことがあるかもしれません。新人職員が抱えやすい悩みを解消する方法を、筆者の経験を紹介します。
参考:厚生労働省|学歴別就職後3年以内離職率の推移、厚生労働省|令和5年雇用動向調査の結果の概況
最初の一歩がいちばん不安――新人介護職員が抱えやすい悩みとは

筆者が新人だった頃、職場では「先輩が仕事をする様子を見て覚えることが当たり前」という風潮がありました。デイサービスに所属していた筆者の周りには多くの職員がいましたが、説明を受けたあとは周囲の動きを見ながら覚えるしかありませんでした。
しかし、先輩たちは常に動いているため、現場でわからないことがあっても声をかけるタイミングが思うようにつかめません。「今、聞いていいのかな」「これくらい自分で判断しなきゃ」と迷っているうちに、自分の手が止まることもありました。
筆者が特に判断に迷ったのは、業務の優先順位や適切なタイミングです。例えば、介助中に別の利用者さんのコールが鳴ってしまう、利用者さんとの会話中に歩行が不安定な別の利用者さんが立ち上がっている、などです。
介護の仕事は判断をひとつ誤ると、利用者さんの怪我や大きな事故につながります。本来であれば自分で判断したり、相談しながら進められる仕事が、新人の頃は判断力や経験が乏しいために、想像以上に心をすり減らすのだと思います。
新人あるある「乗り越え」から学ぶ、悩みの対処法

介護の仕事は、経験を重ねるごとに、落ち着いて対応できるようになります。しかし、新人の頃は何をすればよいのかわからないため、悩みや不安を抱えやすい時期です。
悩みを乗り越える方法は人それぞれ異なりますが、筆者は主に次のような方法で対処しました。ここでは、具体的なエピソードを紹介します。
覚えることを即座にメモする
新人時代は、利用者さんの顔や名前、個々の対応方法など、覚える情報が多いため、頭の中でうまく整理できませんでした。説明を聞いたときは「覚えた」と思っても、業務に追われるうちに内容があやふやになったものです。そのため、あとで同じ場面が訪れたときに「どうしたらいいのかな?」と思うことが何度もありました。
例えば、「Aさんはむせることが増えたので、今日からとろみをつけた食事を提供してほしい」と先輩に指示されていたのを忘れて提供したり、利用者さんの体調変化をメモしておらず、次のスタッフに申し送りを忘れたりしました。
幸いなことに、いずれのケースも他のスタッフが覚えていたため、重大な事故には至りませんでしたが、忘れずにメモしていれば防げたミスです。このような事態に陥らぬよう、介護職でキャリアを重ねた今でも小さなことでもメモに残すようにしています。あとから振り返る際にも役立ち、現場で動くときの安心感にもつながっています。
言い方がきつい先輩と利用者さんに落ち込んだら、適度な「距離感」を取る
新人の頃、怒っているわけではありませんが、きつい言い方をする先輩がいました。しかし、先輩から指導や注意をされているうちに、その人の前では緊張するようになりました。
ある日、先輩が他の職員に対しても同じような言い方をしているのを見かけたことがありました。そのときに「もともと先輩はこういう人なんだ」と割り切るようになったため、先輩とは必要なときに手短に話し、一定の距離を保つようにしました。
先輩だけでなく、厳しい言葉をかけてくる利用者さんもいらっしゃいます。「あんたじゃダメ」「○○さんはいないの?」と言われるたびに、「自分は受け入れられていないのでは…」と思うようになり、へこむことがありました。
しかし、利用者さんに対しても「相性があるのは当たり前」「利用者さん全員の評価ではない」と割り切ることにしたことで、気持ちに少し余裕が生まれました。相手と適切な距離感を取ることで、感情に振り回されずに仕事を続けられたと思います。
完璧主義をあえて目指さない
筆者が新人の頃は、何をするにも「うまくやらなければ」「早く覚えなければ」と焦っていた気がします。同期入社の職員がいなかったため、比較する対象が自然と先輩になり、自分のできないところがやたらと目についたのを覚えています。
先輩に注意されるたびに「ちゃんとやらないと認めてもらえない」「できていない自分には価値がない」と思い込んだこともありました。先輩の指摘には学ぶべき点もありますが、当時はその一言でさえ、重くのしかかっていました。
とある先輩から「焦らなくていいよ。誰でも仕事を覚えるには時間がかかるから」と言われたことをきっかけに、少しずつ気持ちが晴れやかになりました。完璧を目指すよりも、できないことを認め、ミスをしたときに相談できる方が、現場では大切だと気づいたからです。
今思えば、完璧にしたいという気持ちが強く、周囲の力を借りられなかっただけだと思います。「できることからひとつずつ」「わからないときは聞いていい」と思えるようになってからは、仕事も次第に楽になりました。
こんなとき、どうするの?先輩介護士からのリアルQ&A

新人の頃は、現場の判断に迷ったり、対応に困ったりする場面があります。ここでは、筆者が体験したことを振り返りながら、対処法を紹介します。
Q1:心を開かない利用者さんとのコミュニケーションで気をつけることは何ですか?
筆者の新人時代には、自分の弱みを見せたくないのか、利用者さんの中には介助を拒否する、話を聞かないといった心を開いてもらえないことがありました。「自分の対応が悪かったのか」と落ち込む日もありました。
しかし、その利用者さんは介助が必要なうえに、いつでも自分以外の職員が対応できる状況ではありません。その都度、説明をしますが、納得してもらうのには時間がかかりそうです。
この経験で筆者が感じたことは「心を開かない相手とのコミュニケーションに、特別な裏技はない」ということです。時間をじっくりかけて、信頼関係を築くしかないと実感しました。特に意識していたことは、相手のペースに合わせること。焦って心を開いてもらおうとしても、相手の信用を失う可能性もあります。
信頼関係を築くためにも、相手の言葉や態度に一喜一憂せず、自然体で、かつ丁寧な対応が必要です。その積み重ねによって、少しずつ心を開いてくれるからです。
利用者さんの心身の変化で「自分でできないこともある」と受け入れられたことも大きかったのかもしれません。その結果、ようやく穏やかな気持ちで関われるようになりました。
Q2:タイミング的に人手不足になった場合の適切な対処法を教えてください
介護の現場では、体調不良や異動、退職などが重なって人手不足になる場合があります。特に必要最低限の人数で運営している職場では、職員が一人休んだだけでも業務に支障をきたすことが考えられます。
筆者が新人の頃は自発的に動くタイプではありませんでしたが、勇気を出して「自分にできることから積極的に動く」ことを心がけました。新人でも食器の片付けやレクリエーションの準備など、他の職員のサポートができる仕事があるからです。
また、仕事をするうえで大切なのは、全体の動きを観察することです。例えば、「周りの職員は今何をしているのか」「次は何をする時間なのか」といった、「足りない部分」を見つけて動くようにしていました。
ただし、不安なときは先輩に必ず確認していました。小さな疑問でも確認した方が、ミスやトラブルを防ぐことができます。
新人の頃は「役に立ちたい」という気持ちが先走ってしまい、忙しいときほど焦って行動をしがちです。今の自分にできることを着実に積み重ねていけば、先輩からの信頼も得られるようになるでしょう。
Q3:「介護職を辞めたい」と思ったときに、どうやって乗り越えましたか?
介護の仕事は高齢者の生活や命に関わるため、現場で働く人が精神的な負担を感じることも少なくありません。筆者も利用者さんの急な体調の変化や事故を目の当たりにしたとき「辞めたい」と思ったことがありました。
現場スタッフが利用者さんのために尽くしても、事故や急な体調の変化を完全に防ぐことはできません。行動することが大切だとわかっていても、急な出来事に対応できない自分に「この仕事は向いていないのでは」「なかなか成長できない」と、落ち込むこともありました。大事なのは、そうした気持ちにふたをせず、自分なりに受け止めることです。
先輩から「誰でもそういう時期はあるよ」と声をかけてもらったり、利用者さんからの何気ない一言に救われたりして、時間が経てば「もう少し頑張ってみよう」と考え方をポジティブに切り替えるタイミングが訪れるでしょう。
「この介護の仕事をいつまで続けられるか」ではなく「今日一日は、○○を頑張ってみよう」といった小さな目標に切り替えることも、乗り越えるひとつの手段ではないでしょうか。
介護職を続けるためのコツ

介護の仕事はやりがいがある一方で、体力や気力を必要とする場面も多く、長く続けるには工夫が必要です。筆者が実践した5つのコツを紹介します。
・介護職の「よいところ」を見つける
・生活リズムを整える
・周りの職員に助けを求める
・自分の強みを見つけて活かす
・小さな目標を立てる
利用者さんの笑顔や感謝の言葉などの小さなやりがいや、キャリアアップしやすい面、親の介護にも役立つなど、介護のよいところに目を向けましょう。
介護職は不規則な勤務形態のため、体力を維持するためにも、栄養のある食事や十分な睡眠時間が大切です。また、つらいときは遠慮せず周りに助けを求めてください。新人のうちに素直に相談しておけば、チームワークもしやすくなります。
仕事を続けるためには、自分の強みを活かすことも大切です。筆者は工作が得意だったのでレクリエーションの場で役立ち、それが自信につながりました。資格取得のような大きな目標だけでなく「今日は一日○○を楽しんでいただく」「今日はレクリエーション企画を発表する」など、小さな成功体験を積み重ねると、やりがいも持続しやすくなると思います。
これから介護職として活躍するあなたへ

介護の仕事を始めた頃は、利用者さんとの対応や職員同士の人間関係など、さまざまな壁にぶつかるかもしれません。介護職を始める前に抱いていた理想と現実のギャップに悩み「自分には向いていないのでは」と感じることもあるでしょう。
介護の仕事は、介護職員の連携によって高齢者の生活を支えています。うまくいかない日や結果がすぐに出ない日も利用者さんや家族の役に立っています。
つらいときは一人で抱え込まずに、信頼できる先輩や同僚、友人に相談してみてください。話をしてみるだけでも、気持ちが軽くなります。周囲の人の力を借りながら、自分らしい介護職の関わり方を見つけていきましょう。
新人の頃は、誰もが不安を感じながら働いています。大切なのは、完璧に業務をこなすよりも、利用者さんや職員と向き合おうとする誠実な姿勢です。多くの経験を重ねながら、自分なりの「やりがい」や「得意なこと」を見つけ、現場で役立ててください。
コラム記事執筆者

山本史子
介護福祉士
デイサービスで10年以上、介護福祉士として現場勤務を経験。利用者さまに「またデイサービスに行きたい」と思ってもらえる施設づくりを目指し、日々ケアに携わっている。趣味は工作やハンドメイドで、利用者さまとのコミュニケーションにも活かしている。現在は、介護現場での勤務と並行してライターとしても活動中。現場経験に基づき、実用的で温かみのある記事執筆を心がけている。